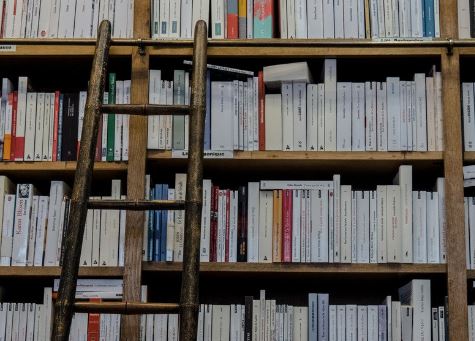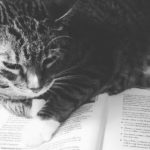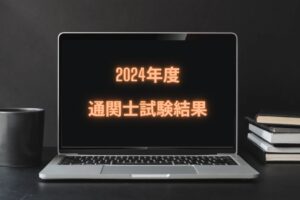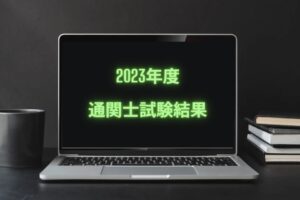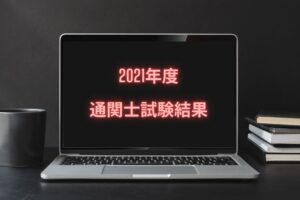通関士試験を独学短期一発合格するための教材について、2つのプランに分けて書いてみました。
教材の選定をする際の参考にしてみてください。
目次
1.合格するための教材の選択
2.2つのプラン
3.Aプラン
4.Bプラン
5.まとめ
1.合格するための教材の選択
2つのプランをご紹介する前に、合格するための教材を選択する上で重要なことについて書いておきます。
試験に合格するためには、テキストを読み込んで理解を深めることは重要ですが、それよりも大切なことがあります。
それは、問題を多く解いて試験の傾向と対策を掴むことです。
傾向や解き方を掴んでおかなければ合格基準に到達するどころか、時間内に解き終わることも難しいかもしれません。
そこで、より多くの問題に取り組んで、より効率的に問題が解けるように、問題慣れしておくことが非常に重要となります。
しかし、ここで問題になるのが、いわゆる悪問です。
通関士の過去問には、必ず悪問(難問・奇問)が含まれていると言っても過言ではありません。
そして、そんな悪問(難問・奇問)の攻略に時間をかけるべきではありません。
それよりも、「正解率の高い基本的な問題で合格基準6割を確実に得点できる」ように対策することが重要です。
正解率の高い問題とは、多くの方が正解することが出来る問題です。
「正解率70%」と言えば、7割の方が正解している問題ということです。
このような正解率の高い問題を絶対に取りこぼしてはいけません。
逆に「正解率10%」などという問題に正解する必要はありません。
それは、いわゆる「難問・奇問」と呼ばれるような問題です。
本試験で、難問・奇問を解くのに時間を奪われて、正解率の高い問題を疎かにしては合格が遠のきます。
通関士試験では、難問・奇問が解ける受験マニアになってはいけないと考えてください。
「正解率の高い問題」を取りこぼさないようにして、6割の合格基準を満たすように得点できれば独学で一発合格できます。
このようなことから、合格するための教材を選択する上では、問題集の選定が非常に重要になると言えます。
2.2つのプラン
以上のようなことを念頭に置いて、2つのプランをご紹介します。
Aプラン
1つ目は、時間に余裕がある場合のAプランです。
これは、テキストは詳細なものを選択して、問題をできるだけ多くこなすというものです。
6ヶ月以上の試験準備期間があり、勉強時間を毎日2時間以上は作れる方に限られてくるプランとなります。
毎日2時間の勉強で6ヶ月ですと、360時間となります。これは少し時間が不足してくるかもしれません。
できれば、毎日2.5時間から3時間程度は勉強する時間が必要であると考えておきましょう。
つまり500時間程度の時間を要すると考えておいた方が無難です。
ボリュームがある分、勉強期間も長くなるため、事前に学習計画をしっかりと立て、進捗管理をしながら軌道修正しつつ、試験対策することができなければ、厳しい計画であるとも言えます。
Bプラン
2つ目は、時間に余裕がない場合のBプランです。
これは、テキストは短時間で全体の流れを把握できるものを選択し、問題集は、「基本・頻出レベル」の問題をピックアップして取り組むというものです。
例えば、当初は時間的に余裕があると思って、Aプランで準備していても、仕事や家庭の都合など様々な理由によって、予定通りに勉強が進まない可能性もあります。
そこで軌道修正が出来なければ、
『「通関実務」に手が回らなかった』とか、
「問題集を十分にこなせずに試験の当日を迎えてしまった」
というような状況に陥る可能性が出てきます。
上述の状況下で合格するのは非常に難しいと言えます。
また、独学に特有の様々なリスクが絡んでくると、予想以上に時間が必要となる可能性もあります。
そういった事態に対処する上で、Bプランのような代替プランを持っているということは重要だと言えます。
今から振り返って思うと、初めからBプランでスタートしておけば、もっと効率的に勉強を進められたと思います。
なぜなら、大多数が正解する正解率の高い問題を予め集中的に学習することができるからです。
「正解率の高い問題」は、「基本・頻出レベル」の問題です。
それらの問題は、「絶対に取りこぼしてはいけない問題」と言えます。
それを予め知ってから試験勉強をすることは、合格への最短・安全ルートを念頭に置きながら着実に歩みを進めることになります。
そして、合格への最短・安全ルートが分かれば、避けて通るべき危険ルートも認識できることになります。
避けて通るべき危険ルートとは、上述の悪問(難問・奇問)をむやみに解き進めるルートのことです。
3.Aプラン
Aプランとしては以下のような教材を使ってしっかりと基礎を固めて、多くの問題を解くようなプランになります。
通関士完全攻略ガイド
通関士過去問題集
通関実務集中対策問題集
また、出版社や著者は違いますが、以下の書籍を概要理解のために追加して使用しても良いでしょう。
分かりやすく概要を素早く理解するのに役立ち、「通関士完全攻略ガイド」を読む際のストレスを軽減できます。
通関士合格の基礎知識
≪注意≫
改定3版が2025年4月に発売予定です。
これらのテキストと問題集を使えば合格レベルに到達可能です。
ただし、計画も進捗管理も全て自分でする必要があります。
また、疑問点が出てきても、自分で解決しなければなりません。
独学で短期一発合格を目指す上では、それなりのリスクを伴う可能性があることにも注意が必要です。
4.Bプラン
独学でのリスクをカバーしつつ、合格のための得点源である、「頻出・基本レベルの問題」を短期間で効率的におさえるという方法です。
この方法での教材選択の際には以下のような条件を満たす必要が出てきます。
・全体の流れをいちはやく把握して問題にとりかかれる
・大多数の人が正解できる「頻出・基本レベルの問題」を確実におさえている
・初学者が独学で短期合格を目指す上でのリスクをカバーできる
この条件を満たすために、通信講座を利用しますが、どの通信講座でも良いという訳ではありません。
「独学」で「短期」と言うリスクを適切にカバーできるかどうかが重要です。
内容面はもちろん、ボリューム的にもリスクをカバーできるものでなければなりません。
例えば、山岳保険を例にとってみると、夏山登山と冬山登山ではリスクが違うので、ピッケルやアイゼンを使う冬山には「冬山専用の山岳保険」をかける必要があります。
海外旅行に行く際にも、行く地域によってはワクチンを打ったり、保険のオプションを追加しておく必要があるでしょう。
独学で短期合格を目指す上での様々な側面で考えられるリスクに対して、最低でも以下のようなオプションを付加できなければ意味がありません。
・コンパクトかつ要点を衝いた講義とテキスト
・隙間時間を利用するのに適した録音倍速教材
・大多数の人が正解できる「頻出・基本レベルの問題」を確実に押さえた問題集
・学習計画立案や進捗管理
・最新情報の取得(法改正・試験形式の変化への対応)
・質問による疑問点の解消
・模擬試験※
※模擬試験は、実績と経験に基づくプロが作った本年度の法改正や試験形式を踏まえた予想問題であり、試験当日をシミュレーションする機会を作ることができることからも、かなり重要なものとなります。
上記の条件を満たした通信講座を見つけて利用できれば、最短コースで合格できる可能性があると言えます。
また、以下のような機材を用いて、さらに効率を高めることも可能です。
やり方は簡単で、2~3倍のより速い速度で再生ができる機材を用いるだけです。
具体的には、通信講座を受講しつつ、以下のような機材に録音してしまいます。
↑3倍速※に対応しているか、是非ご確認ください!
(画像よりアマゾンのページでスペックの確認や他のカラーバリエーション、充電式電池付属モデルなどが確認できます。)
※録音倍速学習には、3倍速に対応したスペックのものをおすすめします。2倍速止まりのものはもったいないので買わないようにしましょう。TOEIC試験対策や会議・研修にも使えます。
上記製品のスペック→ソニーストアの製品情報ICD-PX470F
あとは、それを繰り返し通勤中の電車や車の中で聞くだけです。
車通勤の方は、マスクをして声に出してなぞるようにすれば、より効率的に学習することができます。
英語学習におけるシャドウイングという方法です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
そして、時間に余裕があれば、以下の問題集を追い込みに使えれば万全の備えとなります。
通関士過去問題集
通関実務集中対策問題集
上記のBプランでスタートして、「絶対に取りこぼしてはいけない問題」を先に把握してから、余裕があればAプランのやり方に移行していくという手もあります。
5.まとめ
とにかく問題に多くあたることが重要ですが、その問題の質が重要になってきます。
本試験で大多数が正解してくる可能性の高い「頻出・基本レベルの問題」を選別して、優先的に取り組む必要があります。
他の記事でも述べたように、悪問(難問・奇問)に構う必要はありません。
また、独学ならではの様々なリスクを踏まえて対策することも重要です。
これらのことは、安全ルートを確認した上で山に登り始めるのと同じことです。
一般登山道(安全ルート)を確認せずに山に登ることは、経験豊富なベテランにとっても非常に危険な行為であると言えます。
遭難(不合格)を避けるためにも、安全ルートを確認できるようにしましょう。
さらに、時間という要素も重要です。
「頻出・基本レベルの問題」を優先的に解いて、見直しもできるように時間配分を考えられるようになることが重要です。
時間と言う要素については、「確保できる勉強時間」という点を考えて置くことも大変重要です。
テキストを熟読してから問題にとりかかる余裕はあるのか、良く考えて教材を選択するようにしましょう。
山登りでも天候の急変などがあった場合には、安全に下山するためのエスケープルートを把握しておくは非常に重要なことです。
家事や仕事の都合といった状況の急激な変化により、勉強できる時間が削られてしまった場合でも、別ルートを知っておくことは心の余裕につながります。
そして、「通関実務」に関しては、テキストを読まなくても問題を解いていくことは可能であり、「最優先して早期から着手する必要がある」ということは、通関士試験に独学で短期一発合格する上でのセオリーと言えます。
問題を解けない時は、すぐに解説を読んでみてください。
例えば、現実支払い価格などでひっかかったら、さきほど紹介した「辞書 (通関士完全攻略ガイド)」を引きましょう。
とにかく一刻も早く「通関実務」の問題に着手することが、全科目受験で合格する上では特に重要な課題となります。
なお、テキストと問題集の使い方やその他の参考書籍など、Aプランについてより詳しく書いた記事は以下をご覧ください。
教材(テキスト・問題集・参考書)のまとめは以下の記事をご覧ください。
「問題集の重要性」や「6割を取ることを考える」ということについては、以下の記事をご覧ください。
2022/02/06:リンク先を最新版へと改定