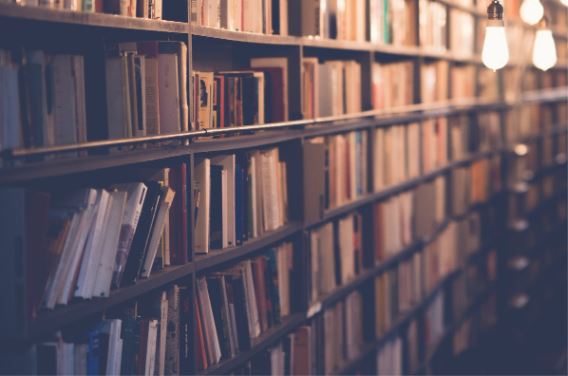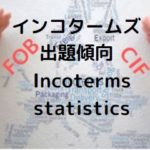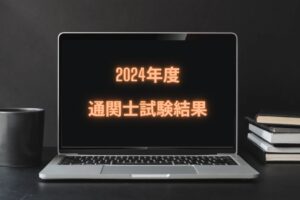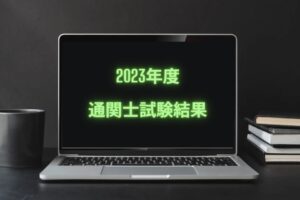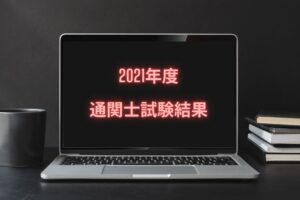通関士試験を独学短期一発合格するためのおすすめテキスト(教科書)、問題集、過去問、参考書などの市販教材についてまとめてみました。
出版社がアピールしている内容はネットや実物で見ることができるため、私の個人的な意見を書くように心がけています。
テキスト(教科書)、問題集、過去問、参考書など、自分で納得の上使用することが重要です。そのために、ネットの試し読みをしたり、書店に足を運んだりして実際に自分の目で見てご自分に合うものを選択することをおすすめします。
目次
1.テキスト(教科書)・問題集を選択する条件
2.テキスト(教科書)
2.1.「通関士合格の基礎知識」
2.2.「通関士完全攻略ガイド」
2.3.「通関士スピードテキスト」
2.4.「通関士試験合格ハンドブック」
2.5.「通関士試験の指針」
2.6.「通関士試験まるわかりノート」
3.問題集
3.1.「通関士過去問題集」
3.2.「通関実務・集中対策問題集」
3.3.「ゼロからの申告書」
3.4.「通関士過去問スピードマスター」
3.5.「通関士テーマ別問題集」
3.6.「どこでもできる通関士選択式徹底対策」
3.7.「通関士試験問題・解説集」
3.8.「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
3.9.「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
3.10.「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
4.その他の参考書
4.1.「仕事の流れが一目でわかる! はじめての貿易実務」
4.2.「貿易物流実務マニュアル」
5.まとめ
1.テキスト(教科書)・問題集を選択する条件
「独学」「短期」「一発合格」というような条件をクリアする上で重要な以下のような条件を満たしているのか確認しつつ、テキスト(教科書)および問題集、過去問集をご紹介します。
①全体の流れをいちはやく把握して問題にとりかかれる
②「頻出・基本レベルの問題」を確実におさえている
③初学者が独学で勉強する場合でも分かり易い説明がなされている
④最新情報の取得(法改正・試験形式の変化への対応)が可能である
⑤学習計画立案や進捗管理が容易である
⑥テキストと問題集の整合性がある
2.テキスト(教科書)
2.1.「通関士合格の基礎知識」
「通関士合格の基礎知識」
著者:片山立志
出版社 : 日本能率協会マネジメントセンター
≪注意≫
改定3版が2025年4月に発売予定です。
字も大きく、図や表を多用しており非常に読みやすく、短期間で読み終えることができます。これから勉強する通関士試験の概要を素早く掴むことができます。
また、初学者にとっては初めは難解に感じる通関士試験の内容を分かり易く説明しています。
このようなことから、合格レベルに到達するためのもっと詳細でボリュームのあるテキストに取り組む際の理解を助け、心理的な負担を軽減することができる良書であると言えます。
ただし、このテキストは本の題名通りあくまでも「基礎知識」を分かりやすく解説した入門書であり、このテキストだけでは合格レベルに到達することはできません。
あくまでも概要を素早く掴み、基礎的な知識を身に着けるためのテキストだということです。
このテキストは、著者の出版しているもっと詳細なテキストとの整合性があることは言うまでもありませんが、
「基礎知識」を扱っていると言う性質上、全てのテキストに整合性があると言っても過言ではありません。
このようなことから、以下の条件をクリアしているテキストと言えます。
①全体の流れをいちはやく把握して問題にとりかかれる
③初学者が独学で勉強する場合でも分かり易い説明がなされている
⑥テキストと問題集の整合性がある
個人的にはおすすめのテキストです。
特に通関士試験に初めて取り組まれる方が最初に読むテキストとして、おすすめの一冊と言えます。
後述するテキストの「通関士試験合格ハンドブック」および、問題集「通関士テーマ別問題集」、「どこでもできる通関士選択式徹底対策」とは著者・出版社が同じで整合性があると言えます。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験合格ハンドブック」
「通関士テーマ別問題集」
「どこでもできる通関士選択式徹底対策」
2.2.「通関士完全攻略ガイド」
「通関士完全攻略ガイド」
著者:ヒューマンアカデミー
監修:笠原純一
出版社: 翔泳社
圧倒的なボリュームで、非常に詳細かつ丁寧な解説となっており、網羅的なテキストと言えます。
そのようなことから、通関士試験の「辞書」と言っても過言ではありません。
したがって、問題集を解きながら『分からない場合は「辞書」として引く』というような使い方もできます。
また、初学者にも分かり易い解説が「理解のポイント」として記載されています。
上述のことは非常に重要なことになります。
なぜなら、問題集に取り掛かった時に分からない部分や説明が不足している部分が出てきても、このような網羅的で分かり易いテキストがあれば、
不明な部分を明らかにして、理解しながら解き進めることができるからです。
さらに、この分厚いテキストを手に取って目次を見るだけでも、どの程度の勉強量をこなさなければならないのか理解できると思います。
このボリュームに問題集を加えた量が合格レベルに到達するための最低限度の勉強量であると言えます。
こういったことから、学習計画立案や進捗状況把握をする上での指針となり得ます。
また、法改正に対応した情報を読者特典としてホームページから閲覧することもできます。
そして、頻出区分を明記した要点整理問題も章末に準備されており、重要度(基本・頻出レベルかどうか)を確認しながら問題を解きつつ知識を定着していくことを意識させるような構成になっています。
後述する問題集の「通関士過去問題集」とも著者や監修、章構成が同じであり、整合性が取れています。
したがって、以下の内容を満たしていると言えます。
②「頻出・基本レベルの問題」を確実におさえている
③初学者が独学で勉強する場合でも分かり易い説明がなされている
④最新情報の取得(法改正・試験形式の変化への対応)が可能である
⑤学習計画立案や進捗管理が容易である
⑥テキストと問題集の整合性がある
また、アマゾンの「試し読み」が可能なので、書店に行かなくてもある程度は閲覧することが可能です。
個人的にはおすすめのテキストです。
使い方の一例は以下の記事を参考にしてみてください。
【整合性の高い問題集】
「通関士過去問題集」
「通関実務集中対策問題集」
2.3.「通関士スピードテキスト」
「通関士スピードテキスト」
著者/出版社:TAC出版
必要最小限の要点に的を絞った内容になっています。
前述の「通関士完全攻略ガイド」とは対照的に、「試験対策上重要な分野だけ」を重点的に解説しているテキストです。
こちらのテキストも全体の流れをいちはやく把握して問題にとりかかれると言えます。しかし、冒頭で紹介した「通関士合格の基礎知識」と比較すると、初学者に対して丁寧であるとは言いにくい内容となっています。
「通関士合格の基礎知識」が高次元のテキストを読み進めるための理解を助けることを目的としているのに対して、
こちらのテキストは、とにかく問題に解答するために必要な要点を明確にすることに注力していると言って良いと思います。
このテキストは、「後述するTAC出版の問題集「通関士過去問スピードマスター」を解くための足場である」と言うと分かり易いでしょうか。
不安定な足場を利用して問題集に取組み、合格に至るまでのルート工作を器用にできる能力を備えた方に最適なテキストであると言えるかもしれません。
このテキストは、試験慣れしている人におすすめの一冊だと私は思います。
以上のことから、以下の内容を満たしていると言えます。
①全体の流れをいちはやく把握して問題にとりかかれる
②「頻出・基本レベルの問題」を確実におさえている
⑤学習計画立案や進捗管理が容易である
⑥テキストと問題集の整合性がある
また、アマゾンの「試し読み」が可能なので書店に行かなくてもある程度は閲覧することが可能です。
ちなみに、法改正に対応した情報提供などのサービスは付属していません。
要点がコンパクトにまとまっているという大きな強みを持っているテキストです。
ただし、このテキストと関連の問題集だけで独学短期一発合格できる方は、予備知識が豊富で能力が高く、かなり試験慣れした方だと私は思います。
【整合性の高い問題集】
「通関士過去問スピードマスター」
2.4.「通関士試験合格ハンドブック」
「通関士試験合格ハンドブック」
著者:片山立志
出版社 : 日本能率協会マネジメントセンター
「通関士合格の基礎知識」に続く、より詳細なテキストとなっています。
通関士試験においては、このテキストと「通関士完全攻略ガイド」が双璧を成していると言っても良いと思います。
試験に出る基本的かつ頻出度の高い範囲を重点的にカバーするように意識して作られており、分かり易い説明がなされています。
また、目次に重要度を明記して、どこが試験に出るかを把握し易いように工夫がなされています。
さらに、模擬試験も付属しており、本番での時間配分に関しても早い段階から意識的に取り組むように配慮して作られています。
後述する問題集(通関士テーマ別問題集)とは、著者と出版社が同じで整合性があると言えます。
日本能率協会マネジメントセンターのホームページからは法改正情報などを見つけることはできませんが、著者が代表を務める以下の会社のHPより法改正情報について確認することができます。
MHJマウンハーフジャパン伝統の通関士通信講座 通関士関連「法令改正」情報
このようなことから以下の内容を満たしていると言えます。
②「頻出・基本レベルの問題」を確実におさえている
③初学者が独学で勉強する場合でも分かり易い説明がなされている
④最新情報の取得(法改正・試験形式の変化への対応)が可能である
⑤学習計画立案や進捗管理が容易である
⑥テキストと問題集の整合性がある
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士合格の基礎知識」
「通関士テーマ別問題集」
「どこでもできる通関士選択式徹底対策」
2.5.「通関士試験の指針」
「通関士試験の指針」
編集:日本関税協会
出版社:日本関税協会
このテキストは、公益財団法人日本関税協会(以下、協会)が出版しています。
特徴を挙げると以下のようになります。
- 高額(6,000円超え)であること
- 難問にも対応できるような知識の習得を目指している
- 税制の優遇を受けている日本関税協会が出版している
- 100㎞以上移動しても置いている書店に辿り着くことができない場合がある
- 通関士試験対策として考えると、賛否両論で意見が分かれることが多い
それでは、価格以外の特徴について説明してみたいと思います。
・難問にも対応できるような知識の習得を目指している
実務レベルに近い知識の習得を目指しており、難問にも対応できる力を養うことができます。
しかし、裏を返せば出題されないような範囲についてもカバーしているとも言えます。
ホームページより引用すると、以下のように特徴を説明しています。
通関士試験範囲を完全網羅し、基本的な事項から細かい通達の規定まで解説図や表を利用して丁寧に解説していますので、どのような問題が出題されてもこれを読んでおけば慌てることはありません。
公益財団法人日本関税協会HP「通関士の指針」
・税制の優遇を受けている日本関税協会が出版している
この協会は、元々は財務省所管の財団法人だったのですが、現在は公益財団法人として存在しています。
日本関税協会とは、財務省所管の財団法人だったが、公益法人制度改革に伴い、2011年4月1日に公益財団法人に移行。
日本関税協会 wikipedia
この協会が主催している通学・通信講座があることは有名ですが、講師は元税関職員や元大蔵省官僚や元財務省官僚となります。
協会のHPより設立趣意を見てみると、
「貿易の実務や、手続きの解説等を行って、一段とその振興を図る」
公益財団法人日本関税協会HP 設立趣意
という目的を持っていることが分かります。
この協会の他社との大きな違いは、「試験に合格させること」を目的としているのではなく、もっと大きな国家的な役割を担っているということです。
・100㎞以上移動しても置いている書店に辿り着くことができない場合がある
さて、このテキストについては、以下のHPより試し読みできますが、ほんの一部分しか見ることができません。したがって、書店に行って実際に手にして読んでみた方が良いと思います。
(公益財団法人日本関税協会HP 通関士試験の指針)
ただし、「全国常備書店」にしか置いていないため、地方在住の方は気軽に試し読みをすることが難しいかもしれません。東京在住の方でも23箇所しか「常備書店」はありませんので、以下のリンクよりご確認ください。
(公益財団法人日本関税協会HP 出版物・資料>全国常備店)
例えば、東北では2県、中国地方では2県、四国地方では1県しか「常備書店」が所在している県はありません。
このようなことから、100㎞以上移動しても常備書店に辿り着くことができない方が地方に行けばたくさんおられることになります。
したがって、近くに「常備書店」がない場合は協会に発注するか、ネットショップで手に入れるしかありません。
アマゾンや楽天で確認すると、時期によってはプレミア価格で高額取引されているのは、このことが原因と言えるかもしれません。
同じように、同協会より出版されている問題集「ゼロからの申告書」が、最新版ではないにもかかわらずネットショップやフリマなどで高額取引されているのも、このような事情があるからかもしれません。
地方在住・経済弱者・情報弱者に対しては非常に厳しい設定であると感じるのは私だけでしょうか。
・通関士試験対策として考えると、賛否両論で意見が分かれることが多い
同協会は、実行関税率表や関税六法なども出版しています。
会社によっては、それらの書籍と一緒にこのテキストを購入している場合もあり、推薦図書となっている場合がありますが、
通関士試験対策としては、出題されないような範囲についてもカバーし、難題も盛り込まれています。
通関士試験対策として使用すべきか考えるときに、賛否両論で意見がはっきりと分かれるのがこのテキストの特徴とも言えるように思います。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験まるわかりノート」
「0からの申告書」
「通関士試験問題・解説集」
「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
2.6.「通関士試験まるわかりノート」
「通関士試験まるわかりノート」
編集:日本関税協会
出版社:日本関税協会
上述のテキスト「通関士試験の指針」の重要部分を要約してまとめたものです。
通関士試験の指針だけでもかなりのボリュームですが、それをさらにA5版でレジュメとした上で、問題が付加されています。
通関士試験の指針に加えてこの本を学習し、さらに協会関連の問題集を5冊こなすと相当なボリュームとなります。
このボリュームの知識を定着させることができれば合格しない方がおかしいと言わざるを得ないでしょう。
仕事や家事・育児をこなしながら、これらのタスクを消化することは何らかのサポート体制がないと到底不可能ではないでしょうか。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験の指針」
「0からの申告書」
「通関士試験問題・解説集」
「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
3.問題集
通関士試験は全般的に、初めて解いた場合はかなりの確率ではミスをしてしまうように作り込まれた問題がたくさん出される傾向があります。
そのために、より多くの問題に取り組んで問題慣れすることはもちろん、効率的に問題を解くコツを掴みミスをしていないか確かめる余裕を持てるようにしたいところです。
さらに、通関士試験には、難問・奇問が出題されることも多く、それらの攻略に時間をかけることは「正解率の高い問題」を取りこぼす要因にもなります。
「正解率の高い問題」とは、大多数が正解することが出来る問題です。
そういった問題は基本・頻出レベルのものであり、それらを取りこぼすことなく6割の合格基準を満たすように得点できれば独学で一発合格できます。
言い換えれば、基本・頻出問題をミスなく効率よく解けるように練度を上げることができたかどうかが、合否を分けると言っても良いでしょう。
このようなことから、テキストの選定にも増して重要なのが、問題集の選定と言うことになってきます。
3.1.「通関士過去問題集」
「通関士過去問題集」
著者:ヒューマンアカデミー
監修:笠原純一
出版社: 翔泳社
本試験と同じ出題形式となっており実践的です。
上述のテキスト「通関士完全攻略ガイド」とは、著者や監修が同じであり、章構成も同じで整合性が良いことは言うまでもありません。
問題は過去問よりピックアップされており、出題頻度分類や難易度分類も一目で分かるようになっており、基本・頻出レベルを中心とした問題に取り組み易くなっています。
問題に取り組んだ日付を書く欄を設けるなど、進捗管理にも意識して取り組めるように配慮がなされています。
前年度の過去問が模試として付属しており、本試験での時間配分を意識して取り組めるような配慮もなされています。
また、法改正に対応した情報を読者特典としてホームページから閲覧することもでき安心です。
これだけでは通関実務が少し手薄になりますが、後述の著者や監修が同じである通関実務特化型問題集である「通関実務集中対策問題集」を組み合わせると、合格レベルに到達することが可能だと思います。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士完全攻略ガイド」
「通関実務集中対策問題集」
3.2.「通関実務集中対策問題集」
「通関実務集中対策問題集」
著者:ヒューマンアカデミー
監修:笠原純一
出版社: 翔泳社
通関実務対策はある程度の数をこなしておく必要があります。
特に「ミスを誘う仕掛けを見抜く眼」や「ミスを見落とさない注意力」、「難問を見抜いて後回しにする見切りの良さ」、「問題を素早く処理する練度の高さ」などを養うことが重要になってきます。
この問題集はこれらの能力を養う上で適切なレベルの問題集であると言えます。
できるだけ多くの問題を解いて、難問も解けるように努力する必要があると言う方もおられるようですが、私は必ずしもその必要はないと思います。
なぜなら、多くの問題や難問をいくら解いたところで、仕掛けを見抜く眼や問題を素早く処理する能力を養えていなければ、0からの状態で本試験に挑むのと同じだと思うからです。
標準的な問題をある程度の範囲で反復して解き、処理能力を上げることが最も重要ではないでしょうか。
また、メインと捉えられがちな輸出入申告書作成問題だけでなく、計算問題、商品分類問題もバランスよく得点できていなければならないことは言うまでもありません。
このような観点から見て、この問題集は適切なボリュームであると思います。
ちなみに、この問題集は私の実践したプランの一部として具体的な形で書いていますので、以下の記事を参考にしてみてください。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士完全攻略ガイド」
「通関士過去問題集」
3.3.「0からの申告書」
「0からの申告書」
編集:日本関税協会
出版社:日本関税協会
通関士試験を受験する上で、知らない人はいないと言っても過言ではない問題集です。
この問題集を解くことが通関士試験合格のために絶対必要と言われる方もおられるようですが、私は「余裕があるならば、解いておいても良い」程度であると思います。
特徴としては、最高峰の難易度の問題を含んだ問題集であると言うことです。
そして、テキストと同様に「試し読み」がネット上ではほとんどできない上に、常備書店に赴かなければ手に取ってみることも難しい問題集です。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験の指針」
「通関士試験まるわかりノート」
「通関士試験問題・解説集」
「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
3.4.「通関士過去問スピードマスター」
「通関士過去問スピードマスター」
著者/出版社:TAC出版
上述の「通関士スピードテキスト」とは、著者/出版社が同じであり整合性があると言えます。
アマゾンの試し読みも可能です。
非常に簡潔で分かり易い説明となっています。
過去10年分の過去から抽出し、改変した内容となっており、重要度が星マークで表示されています。
「ひっかけ注意」や「発展問題(難問)」と言った分かり易い標識も設置されており、意識を集中させるべきポイントを明確に指摘しています。
模擬試験も前年度の過去問を利用して解説付きで付属しており、本試験での時間配分を意識して取り組めるような配慮もなされています。
ただし、通関実務の問題数が圧倒的に不足すると言う欠点を抱えています。
この「スピード」シリーズには、テキストと当問題集のみであり、最重要視して取り組むべき通関実務を補強する問題集が見当たりません。
通関実務をどのように補うのか、他の出版社の問題集や通信講座などの利用を検討する必要があると言えます。
【整合性の高いテキスト】
「通関士スピードテキスト」
3.5.「通関士テーマ別問題集」
「通関士テーマ別問題集」
著者:片山立志
出版社 : 日本能率協会マネジメントセンター
出題頻度の高い問題を中心に作成されているため、基本・頻出レベルに特化している良書だと言えます。
「通関士試験合格ハンドブック」を書店でご覧になられ、そちらを選択された方は、こちらの問題集を使用すると整合性があって良いかもしれません。
ネット上では試し読みができませんが、たいていの書店に置いてある書籍ですので、書店にて中身を見てみることをおすすめします。
日本能率協会マネジメントセンターのホームページからは法改正情報などを見つけることはできませんが、著者が代表を務める以下の会社のHPより法改正情報について確認することができます。
MHJマウンハーフジャパン伝統の通関士通信講座 通関士関連「法令改正」情報
前述のテキスト「通関士合格の基礎知識」および「通関士試験合格ハンドブック」とは著者・出版社が同じで整合性があると言えます。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士合格の基礎知識」
「通関士試験合格ハンドブック」
「どこでもできる通関士選択式徹底対策」
3.6.「どこでもできる通関士選択式徹底対策」
「どこでもできる通関士選択式徹底対策」
著者:片山立志
出版社 : 日本能率協会マネジメントセンター
配点の高い語群選択式問題に的を絞り、法改正も踏まえつつ問題が収載されています。
たいていの書店には置いてある問題集です。
前述のテキスト「通関士合格の基礎知識」および「通関士試験合格ハンドブック」、「通関士テーマ別問題集」とは著者・出版社が同じで整合性があると言えます。
通関士試験の全試験科目の問題を一度解いてから、通関実務の強化が完了した後で、ダメ押しで取り組む問題集だと思います。
時間の余裕がある方は取り組むべき価値のある問題集です。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士合格の基礎知識」
「通関士試験合格ハンドブック」
「通関士テーマ別問題集」
3.7.「通関士試験問題・解説集」
「通関士試験問題・解説集」
編集:日本関税協会
出版社:日本関税協会
「過去3年の本試験問題」をそのまま掲載して解説を加えてあります。
「科目別順等」は過去10年の試験問題を、出題頻度別に並び替えて、6割程度の実力がつくように配慮した内容となっています。
上述のテキスト「通関士試験の指針」と問題集「0からの申告書」とセットで取り組むべき問題集と言えます。
この問題集を手に取って使用するかどうかは、あなた次第です。
実際に手に取って見て判断されることをおすすめします。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験の指針」
「通関士試験まるわかりノート」
「0からの申告書」
「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
3.8.「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
編集:日本関税協会
出版社:日本関税協会
日本関税協会が出版している補習問題集です。
課税価格に参入される加算要素のどのようなものがあるか、記述式の問題が収載されていたりします。
「補習」とは学習の不足を補うため、正規の授業時間以外に勉強することです。
上述のテキスト「通関士試験の指針」と「通関士試験まるわかりノート」に加えて問題集の「0からの申告書」、「通関士試験問題・解説集」に取り組んだ後で、さらに補習としてこちらの問題集を解いておかなければ不足があると言うことでしょうか。
もしくは、通関士試験に不合格になった方の補習用として用意されているのかもしれません。
この問題集を手に取って使用するかどうかは、あなた次第です。
実際に手に取って見て判断されることをおすすめします。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験の指針」
「通関士試験まるわかりノート」
「0からの申告書」
「通関士試験問題・解説集」
「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
3.9.「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
編集:日本関税協会
出版社:日本関税協会
日本関税協会が出版している補習問題集です。
税額計算と課税価格計算に的を絞った問題集です。
上記以外は、「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」と同様の説明になりますので省略します。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験の指針」
「通関士試験まるわかりノート」
「0からの申告書」
「通関士試験問題・解説集」
「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
3.10.「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
「通関士試験補習シリーズ通関手続ドリル」
編集:日本関税協会
出版社:日本関税協会
日本関税協会が出版している補習問題集です。
配点ウェイトが高い「通関手続」に絞った問題集です。
上記以外は、「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」と同様の説明になりますので省略します。
【整合性の高いテキスト・問題集】
「通関士試験の指針」
「通関士試験まるわかりノート」
「0からの申告書」
「通関士試験問題・解説集」
「通関士試験補習シリーズ関税評価ドリル」
「通関士試験補習シリーズ計算問題ドリル」
4.その他の参考書
貿易の具体的な流れを理解するために持っておくと便利なおすすめの参考書です。
ちなみに、通関士試験に合格する上で必要な貿易に関する基礎的な知識は、当サイト内に関連記事があるので、そちらをご覧ください。
4.1.「仕事の流れが一目でわかる! はじめての貿易実務」
この本は、税関職員は貿易実務の中でどのような場面で登場するのか、その他の関係当事者はどの場面で顔を合わせたりメールや電話でやり取りすることになるのかを具体的に把握する際に便利です。
貨物の具体的な流れが理解しにくい方や、実務的な書類のやり取りがどのようになっているか知りたいという方にとっても、読んでみる価値があると思います。
輸出や輸入などのシチュエーションごとに、どういった関係当事者が絡むようになるのかイラストと図で理解しやすくなっています。
4.2.「貿易物流実務マニュアル」
非常に詳細かつ実務的な書籍です。初学者の方にとっては少し難しい内容となっているかもしれませんが、実務に即した本物の知識を得られる専門書籍です。
分からないことがあれば、「辞書」として使うことができます。
「インコタームズの費用・危険負担」や「輸出入価格構成要素」などについて分かり易く、根本的な理解をしたい場合はこの本が良いでしょう。
中途半端な値段とボリュームの貿易に関する書籍を買うぐらいなら、思い切ってこれを購入されることをおすすめします。
5.まとめ
自分に合ったテキスト(教科書)と問題集や過去問集を見つけることができれば、
後は、とにかく問題をこなしながら復習しつつ、練度を上げていくことが重要です。
練度を上げる際には、質の高い問題に反復して取り組むことが大切です。
ちなみに質の高い問題とは、
「大多数の受験者が正解する可能性が高い頻出・基本レベルの問題」です。
そして、時間的な制約のある中でミスを誘うような問題を見分ける目を養うことも重要になってきます。
さらに、難問・奇問を見分ける目を養うことも重要です。
なぜなら、本試験で難問・奇問に時間を取られて頻出・基本レベルの問題を取りこぼせば、合格基準に到達できない可能性が高くなるからです。
あくまでも見分ける目を養うことが重要であり、必ずしも難問・奇問を解けるようになる必要はありません。
「頻出・基本レベルの問題」を解けるようにすれば自ずと、難問・奇問の類は回避できるようになります。
テキスト(教科書)が上空から俯瞰視点で見た縮尺の小さな地図だとすれば、
問題集や過去問集は分岐路や傾斜などが分かりやすい大きな縮尺の地図や標識のようなものです。
どちらが間違っていても致命的です。
しかし、問題集や過去問集が間違っていれば道に迷う可能性はより高くなります。
例えば、登山する際に「一般的ルート(安全ルート)」とは違う沢や崖などを通る「困難なルート(バリエーションルート)」をいくつも示してある地図があったとしても初心者にとっては何の意味もありません。
むしろ、道迷いの原因となって、最悪の場合は遭難するかもしれません。
安全ルートを指し示したテキスト(教科書)と問題集、過去問集を購入できるかどうかが、独学で合格するための必須条件と言えるかもしれません。
さらに、勉強できる時間がどのぐらい残されているかという点を考えてテキスト(教科書)や問題集、過去問集に取り掛かることも重要です。
問題を反復して解いて練度を上げる時間的な余裕はあるのか、良く考えて教材を選択するようにしましょう。
なお、私が実践していたテキスト(教科書)と問題集、過去問集の使い方の具体例は以下の記事をご覧ください。
参考になれば、幸いです。